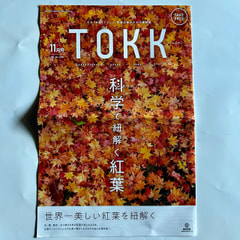
11月の予定
11月3日文化の日10時〜14時 特別文化財公開
11月5日日曜日8時〜9時 真言禅の会
11月8日火曜日14時〜15時 写経の会
11月10日金曜日14時〜15時半 写仏の会
11月15日火曜日14時〜15時 文化財公開
11月19日日曜日 もみじまつり
11月23日祝日10時〜14時 特別文化財公開
MENU
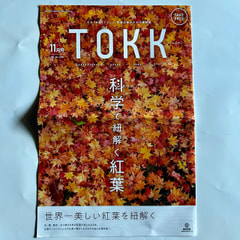
11月3日文化の日10時〜14時 特別文化財公開
11月5日日曜日8時〜9時 真言禅の会
11月8日火曜日14時〜15時 写経の会
11月10日金曜日14時〜15時半 写仏の会
11月15日火曜日14時〜15時 文化財公開
11月19日日曜日 もみじまつり
11月23日祝日10時〜14時 特別文化財公開

10月1日日曜日真言禅の会
10月8日日曜日写経の会
10月10日火曜日写仏の会
10月15日日曜日文化財公開
10月28日土曜日不動護摩祈祷

9月下旬は、御影供や彼岸会、不動護摩祈祷などございました。また、文化財公開の日や参拝も含め、久安寺に足を運んでいただいた皆々さまに心より感謝を申し上げます。
9月の終わりは、ヒガンバナのほか、椿が実をつけたり、酔芙蓉も綺麗だったりという頃だったでしょうか。
酔芙蓉は、朝は白色をしていますが、夕方になるについれて濃い桃色に変化していきます。それが、まるで人がお酒を飲んで、顔色が赤く色づいていくかのように見える。それで「酔う」という字がつけられたのだとか。一日花で、しぼむように閉じてポトンと落ちていく。その一連がとても雅だなと感じてなりません。
そして、久安寺に秋を知らせるかのように、境内にふと現れたキノコたちを「あ!」と発見(笑い)。
それを見ながら、芸術の秋ならぬ妄想の秋が頭の中で膨らんで。キノコたちが人の寝静まった頃、境内を練り歩いたり、中秋の名月の下でダンスをしていたり、なんてそんなことがあったら楽しいなと。
そう言えば、中秋の名月と言えば今年は満月でしたが、毎年必ずしもそうとは限らないんですって。
次に満月と重なるのは、確か7年後だったか、8年後だったか。
その頃の自分はどう過ごしているのだろうか……。皆さまは、どんなワクワクを想像するでしょうか?

彼岸花は、暑過ぎると咲かず、秋の涼やかな気温を好むとな。
真っ赤と真っ白な色で咲く「曼珠沙華」とも呼ばれるヒガンバナですが、今年は9月半ばを過ぎても夏感が強いからか、例年ならたくさん咲いているはずの頃に、まだヒガンバナがあまり咲かずな状況で。
「咲かないなあ、本当に咲かないなあ」と何度も口にしてしまったくらいですが、お彼岸と重なる頃になって、やっとちらほらと美しい姿を見せ始めてくれました。
ヒガンバナは、お釈迦さまが暮らす天上の一面に咲き広がっているのだといわれています。
もしかすると、ヒガンバナが私たちのいる此岸が暑すぎて「いやだ、まだ暑くて咲きたくないよ」と言い、そこにお彼岸時期に彼岸からやって来たお釈迦さまに「これこれ、そろそろ咲いてあげなさいな」と背中を押されてやっと咲いたのだろうか?なんてことを思ってみたり(笑い)。
久安寺には、赤と白の両方のヒガンバナが咲きます。
花言葉は、どちらも「また会う日を楽しみにしているね」とな。
お彼岸は、此岸と彼岸が最も近づくときであり、此の岸から「彼の岸」に到る徳目について考え、平素の日常を見直し、あとは「布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧」これら六波羅蜜行を実行するのみ!ですよ。

二十四節気「白露」、夜のうちに大気が冷え、明け方、草木に白露が宿るようになりて……
ちょうどその白露に当たる日が、9月の写経の会でありました。また、それから数日後には写仏の会もございましたね。ご参加いただいた皆さまに感謝です。
文字をなぞり書いて心を整える、絵をなぞり描いて心を整える。おすすめでございます。
さて、毎年9月になると久安寺に落下する実……と言うと、何だか不可思議な話でも始まりそうですが、今年も「榧の実」の落下を見つけ、そこに近寄ると割れた中の実は食べられた形跡が。
豊臣秀吉公お手植えの榧の木、そして参道の「町のお地蔵さま」のそばにある榧の木。そこから落ちた実をヤマガラが降りてきてはパクパク、モグモグと食べるとな。
そう言えば、ちょっとヤマガラについて調べたところ、日本と朝鮮半島と台湾にしかいない鳥なのだとか。
そして、留鳥(りゅうちょう)というとな。渡り鳥、漂鳥(ひょうちょう)のようにあちらこちらには行かず、その地に根づくタイプであられると。
人懐っこい鳥だとも聞くのですが、あれ……ヤマガラの姿ではなく痕跡しか目にしていないのは気のせいでしょうか(笑い)。皆さまは久安寺でヤマガラにお会いしましたか?

9月初旬、8月が過ぎて「ああ、やっと秋が来たか」と思いたいところでしたが、今年の夏は例年と比べて暑さが本当に厳しく、9月に入ってもなお残暑。いや、「夏の残り」というよりも「夏の中」というのか、まだまだ入道雲にすっぽりと包まれている気がしておりました。
しかしかながら、月の入れ替わりに気を引き締めなければと背筋を整え、まずは真言禅の会から9月の月例行事を皆さまと共に行いました。
先月はお盆時期等で少し開催行事が違いましたが、やっぱりこうして皆さまと体験し、共に時間を過ごすひとときは、とても大事なものだと感じます。
月例の真言禅の会は、第一日曜日の朝8時から開きます。食事(ご飯とお味噌汁のみ)拝観料込み、奉納は1,000円。
気づけば今年も片手で足りる月数になりましたが、初めての方、再会できる方々とのご縁どちらともに大歓迎でございます。
久安寺に来るときだけでも日頃の喧騒から離れ、朝の空気を感じながら、静かな時間を共に持ちましょう。
そして、ぜひ境内に咲く花々にも会っていかれてくださいませ。

9月になりました。残暑きびしく。
月例行事 初めての方、大歓迎です。
3日8時 真言禅の会
8日14時 写経の会
10日14時 写仏の会
15日14時 文化財公開の日
28日14時 不動護摩祈祷の日
21日14時 御影供
23日11時 彼岸会

8月も半ばを過ぎた頃、久安寺・参道には真っ白な鉄砲百合がきれいに咲いてくれていました。桃色の蓮も美しかったですが、この白さにも目を奪われてしまいます。
花言葉は「純潔」としても知られていますが、ほかに「威厳」というものもあります。私は、後者のほうがお盆の月ということもあってしっくりくるというのか、その百合の姿から威光や厳かさが放たれている気がして、ご先祖さまを迎える神聖な花のように見えてしまうのです。
施餓鬼会や地蔵盆の頃がとても見頃だったでしょうか。
施餓鬼とは、亡くなった後、飢えや渇きといった餓鬼の道をさまよってしまう魂、無縁仏となってしまった魂に対し供養を行う法要となります。
そして地蔵盆とは、自分たちの住む土地、そこに住む子供たちをいつも守護してくれるお地蔵さまに対し手を合わせ、お供えを行うものになります。
後者、地蔵盆の縁日は24日に行い、20時から地蔵堂にて御法楽を行いました。その翌日には、町内6ヶ所を巡回し、各お地蔵さまの前にて御法楽を。作法は「おんかかかびさんまえいそわか」です。
そのセッティングをお手伝いいただきました檀信徒総代さんや町内の皆さまに、この場を借りて御礼を申し上げます。

8月半ば17日の日、2週間に亘る檀家様のお家・お仏壇のお盆のおまいり、今夏の棚経を無事に終了いたしました。また、その翌日は久安寺にて施餓鬼会があり、14時より薬師堂にて厳修を。皆さまと一緒に修められましたことに感謝、感謝です。
最近は、毎年何年ぶりの猛暑、何十年ぶりの酷暑なんて言われ方を夏になると耳にしてばかりですが、確か世界のニュースだったか何かによると「今年は地球上で12万年ぶりの暑さ」だとも言われていました。今夏はラニーニャ現象の影響で猛暑になっているらしく、帰ってこられたご先祖さまも、夏の暑さ「熱射病、熱中症、日射病」などと言い方は様々ですが、皆さまの体を心配されているのではないかと思います。
また、「熱中症対策には水分を」とよく言いますが、水だけでなく適度な塩分も必要なのだと。なかなか暑くて食欲が出ないかもしれませんが、朝ごはんにお味噌汁を食べるのもその対策の一つだと聞きます。
8月を過ぎても「秋らしさ」を感じるのはまだまだ先の気がしますので、どうか皆さま、ご自分の健康を第一に考えお過ごしください。そして、もし余裕があるときには、少しだけでも周りの人も気にかけてあげられたらと。そんな優しい世界があちらこちらに広がったらよいなと、常々思っております。
暑い中にもかかわらず、皆さま、夏の久安寺に足を運んでいただき本当にありがとうございました。

8月はお盆の時期であり、真言禅の会をはじめとした定例体験はお休みでしたが、初旬、蓮の花が大きく開き、中の蓮華座がしっかり見える中、久安寺・仏塔にてお盆の法要「盂蘭盆会」がございました。
蓮華座と言えば、お釈迦様が腰をおろしている台座であり、よくお釈迦様のそばには蓮の葉っぱが一緒に描かれることも多い。そして、極楽浄土には蓮が咲き広がっているのだと。
昔から蓮は「おしゃかさまの花」と言われますから、その蓮こそがお釈迦さまのようであり、お盆を一緒に迎え過ごしてくれると思うと、ありがたや、ありがたやと感じるばかり。
さて、お盆と言えば、皆さまのご先祖さまが天上より戻ってこられるときで、盆の入りから盆の明けまでをこちらで過ごされます。また、この期間に合わせて、胡瓜、茄子と割り箸を使ってお馬やお牛を作り、盆の入りには胡瓜の精霊馬を使ってもらい、盆の明けには茄子の精霊牛を使ってもらうためにとご先祖様に用意をされるでしょうか。何でも、胡瓜のほうがスピーディーで茄子のほうがスローリーだと。それで行きには胡瓜を、帰りには茄子を使ってもらうのだとか。
最近では、バイクや車などの形にアレンジをして作られる方もいるようで、「精霊バイク」、「精霊カー」といった現代風な行き来をされるご先祖様も?
そう考えると、空飛ぶバイク、空飛ぶクルマ、何だか私たちよりもご先祖さま方のほうが近未来を過ごされているのかもしれませんね。